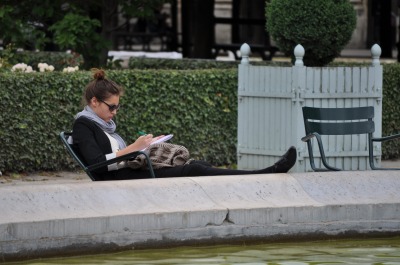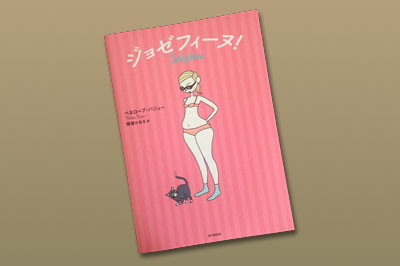パリジェンヌとモード
最終更新日:

夏の公園で語らうパリジェンヌ
モードとは何か?
昔から日本のファッション雑誌ではモード(mode)という言葉がよく使われています。「最新のファッション」を表現する言葉としてすでに日本語でも定着しています。もともとモードとはフランス語で「流行、様式、方法」という意味の言葉です。現在では主に「パリを中心としたファッション業界(服飾業界)」を意味する言葉として使われることが多いです。モードは宮廷文化を中心に中世からありましたが、現代のパリのモードの流れが生まれたのは19世紀。パリでオートクチュール(高級仕立服)というシステムができたことにより最新のファッションという概念が生まれ、メディアの発達によって一般の人々に広まりました。現在では年2回のコレクション発表(ファッションショー)が行われ、「パリコレ」として日本でも知られています。
現代パリのモードの誕生
19世紀後半、ナポレオン3世の主導のもとセーヌ県知事オスマンによるパリ改造がありました。街が大きく変わることで、社会の仕組みも変化しました。新しくなったパリではメディアが発達し、ファッション雑誌が隆盛を極め、多くのパリジェンヌがモードを知るようになりました。メディアが作り出した流行です。印象派の画家オーギュスト・ルノワールの作品に『モード誌を読む女性』(1880)という絵がありますが、これは当時多くの女性がモード関連の雑誌を読んでいたことをよく表わしています。またパリ改造によって街並が中世の汚れた路地から近代的で衛生の行き届いた大通りに整備されたため、「美しい服を着たい」という欲求が高まったこともモードへの関心が生まれた理由のひとつでした。19世紀末はパーティーの時代で、貴族から庶民まで多くのパリジェンヌが着飾って男性と踊り、様々なパーティーを楽しみました。貴族は皆から注目されるために美しい服を着てオペラ座へ行き、庶民はパリ郊外のガンゲット(大衆的なダンスホール)などで着飾って踊りました。ルノワールの『ムーラン・ドゥ・ラ・ギャレット』はそんな庶民のパーティーシーンの幸福な瞬間をとらえた作品といえます。このように改造後の新しいパリでメディアや余暇の概念が生まれたことで、人々の中にモードへの関心が生まれていきました。パリコレの基礎となったオートクチュールの誕生
19世紀、モードに関心が集まることで、パリでは美しい服への需要が拡大しました。そのため服を効率的かつ大量に生産する必要性がでてきました。このとき出てきたのがオートクチュールhaute couture(高級仕立服)というシステムです。当初パリでは様々なオートクチュールのお店が乱立し、その規格も曖昧でしたが、イギリス人のデザイナーであったシャルル・フレデリック・ウォルトがパリでその基礎を築き組織化しました。それまで顧客の一方的な注文によりデザインしていた「顧客主導」の服制作を、デザイナーがあらかじめデザインした服を顧客の体に合わせて仕立てる「デザイナー主導」の服制作へと変更し、大きな成功を収めたのです(いくつかのデザインの型を用意して、その中から顧客に好きな型を選ばせるスタイル)。このとき実際の人間に服を着せて顧客に披露して販売する方法を作り出し、これが現在のモデル(マヌカン)という職業の発端になりました。この方式によってデザイナーとモデルの地位は格段に高まり、現在のパリコレのスタイル(アトリエ制作、専属マヌカン、衣装発表会)の元になりました。このように今では流行という意味で使われるモードという言葉は、19世紀に隆盛したオートクチュールの「型」と深い関係があることが分かります(フランス語のmodeの原義は「型、形式、様式」)。またオートクチュールの高級な服を着るパリジェンヌは多くの画家たちを刺激しました。ルノワールやエドゥアール・マネ、メアリー・カサットなどの画家たちがそんな流行のパリジェンヌたちの日常を描きました。オートクチュールは高級なため、一部の上流階級の女性だけが購入しましたが、庶民はオートクチュールの代わりとしてデパートで服を買ったそうです。
オートクチュールの衰退とプレタポルテの誕生
しかしウォルトの築いたオートクチュールもポール・ポワレの20世紀的でシンプルなデザインやより効率的なプレタポルテ(Pret-a-porter)の登場によって徐々に衰退していきます。プレタポルテは大量受注が可能な高級既製服で、英語の「着られる準備がしてある」という意味のready to wearをフランス語に置き換えた造語です。フランスの既製服メーカーであったヴェイユ社が広告のキャッチコピーとして使用したのがはじまり。それまでは質の低い安価な既製服が出回っていましたが、それらと区別するためにプレタポルテという言葉が作られました。いわゆる「高級ブランド」の誕生です。プレタポルテの全盛によって、オートクチュールとしてのウォルトの店は1954年に閉鎖されます。この頃にはプレタポルテの品質も向上し、オートクチュールに匹敵する服が製作されるようになっていました。ピエール・カルダンやイヴ・サン・ローラン、ソニア・リキエル、高田賢三などのデザイナーがプレタポルテの店を開店し、パリのモードを牽引するようになりました。そして世界最大のプレタポルテ展示会として有名なパリコレはファッション市場が活性化した1960年代から開かれるようになり、現在も毎年そのコレクションが注目されています。また2017年10月より、パリ16区にあるピエール・ベルジェ - イヴ・サン=ローラン財団の施設がイヴ・サン=ローラン美術館としてオープン予定で、パリのファッションに興味ある方には是非訪れてほしい観光スポットとなりそうです。ここでは5000点以上のオートクチュールのほか、15000点ほどの装飾品、彼の描いたデッサンなどが展示される予定です。オートクチュールの中には映画のために制作された服も含まれており、カトリーヌ・ドヌーヴが『昼顔』(1967)で着用した服も見ることができます。ピエール・ベルジェ - イヴ・サン=ローラン財団はイヴ・サン=ローランを支え続けてきたピエール・ベルジェがイヴ・サン=ローランの40年間に渡る仕事の記録、オートクチュール、アクセサリー、デッサンなどを保存するために設立した財団です。今までは美術館ではありませんでしたが、以前より定期的にファッション・絵画・写真・デッサンなどの展示会が開催されており、美術館として生まれ変わったあとは更なる充実したファッション展示が期待できそうです。
今見ると奇抜な当時のモードとは?
現在の流行がそうであるように、19世紀末に流行ったモードのほとんども熱狂的でありながら一過性のものでした。その中でも特にパリジェンヌの間で流行ったのがクリノリン(crinoline)です。これはスカートを膨らませるために発明された骨組みのある下着で、1850年代から1860年代にかけてパリで大流行しました。クリノリンとは馬の尻尾の毛を意味するクラン(crin)と麻布を意味するラン(lin)の合成語。ヨーロッパの昔の絵や版画などでそのデザインを見たことがあるかもしれません。当時上流階級から庶民まで多くのパリジェンヌが異常な準備時間をかけて履いたクリノリンを身に着けてパリを歩き、それはときに滑稽な風刺画の対象となりました。需要が高まった1860年代には、大量生産のためのクリノリン専門の工場ができたほどでした。しかしクリノリンは女性の身体を過度に締め付ける設計だったため、体の内臓の形を変えてしまうほどの危険性があり、またクリノリンを身に着けた女性による転倒や暖炉の火がスカートに引火したりなどの事故が多発したため、次第に廃れていきました。1880年代にクリノリンに代わって流行となったのがバッスル(Bustle〈英〉/Tournure〈仏〉)です。クリノリンがスカート全体だったのに対して、バッスルはお尻の部分だけ膨らんだ構造で、明治時代の日本でも流行したそうです。しかしコルセットが身体をきつく締め付けたため、この流行はすぐに終わりました。このような一過性のモードは、ジョルジュ・スーラやギュスターヴ・カイユボットなどの画家たちによっても描かれています。
そのほかにも19世紀には帽子が流行し、パリ市内には多くの帽子屋がありました。帽子屋は客から注文を受け、完成した帽子を客のアパルトマンまで届けにいきました。ジャン・ベローの『シャンゼリゼ大通りの帽子屋』やドガの『帽子屋』を見ると、当時のパリの帽子屋の様子がよく分かります。しかし帽子には鮮やかな装飾のために鳥の羽が大量に使われたため、多くの希少な鳥が絶滅したといわれています。
20の世紀のモードへ
オートクチュールやクリノリンなどを経て、流行は20世紀になって新しい時代を迎えます。ポール・ポワレがコルセットなしの、体を締め付けないゆるやかでシンプルなデザインの服を考案し、彼女はパリのモードのリーダー的存在となりました。19世紀の装飾過多なモードとは一線を画したこのデザインは新しい時代の到来を予感させ、現代パリのモードへとつながっていきます。そして今ではプレタポルテのデザイナーが注目されると同時に、多くのパリジェンヌが自分だけのスタイルを確立し、モードの意味も大きく変容しています。上流階級だけでなく庶民にまでモードが広まったのが19世紀の特徴でした。パリのモードは上流階級だけでなく、一般の人々も一体となって作り上げられていったもので、それが形を変えて現在のパリジェンヌにつながっています。
現在のパリのモード
最近のパリジェンヌにとって、いかに安く素敵な服を手に入れるかということが最重要課題になっています(フランス人はヨーロッパの中でも服飾関係に関する消費量が少ない)。世界のメディアが注目するフランスのモードの祭典であるパリコレは、パリジェンヌにとっては注目するものではないようです。高級店よりデパートやブティックのソルド(バーゲン)が人気ですし、安い服を手に入れるために蚤の市へ掘り出し物を探しに行くことも多いです。そして使えるものであれば親や祖母のお古を再利用し、自分流にアレンジして着こなしてしまう。随筆家小門勝二は「パリジェンヌは、決してきらびやかなよそおいをして、派手な歩きかたをしているわけではない。いや逆だ。ちょっと見は地味で質素で、どこの堅気の家の娘さんかとおもわれる」と言っています。となると、パリでごく普通の暮らしをしている女性こそがパリジェンヌと言えるのではないでしょうか。祖母や母がパリジェンヌだったように、自分もその伝統の中に入る。そして伝統的でありながら自分の道を行く自信に満ちている。パリジェンヌとパリは歴史の中で深く結びついています。パリジェンヌのおしゃれを学ぶことは、究極の自分らしい生き方につながるのかもしれません。
パリ観光サイト「パリラマ」に関しまして
パリラマはパリを紹介する観光情報サイトです。パリの人気観光地からあまり知られていない穴場まで、パリのあらゆる場所の魅力を提供することを目的としています。情報は変更される場合があります。最新情報はそれぞれの公式サイト等でご確認ください。
パリラマはパリを紹介する観光情報サイトです。パリの人気観光地からあまり知られていない穴場まで、パリのあらゆる場所の魅力を提供することを目的としています。情報は変更される場合があります。最新情報はそれぞれの公式サイト等でご確認ください。
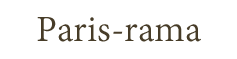 パリ観光サイト「パリラマ」
パリ観光サイト「パリラマ」