オペラ座
最終更新日:
豪華絢爛なパリの社交場
オペラ座(オペラ・ガルニエ)はパリで最も有名な観光地の一つ。ルイ14世によって設立された王立音楽アカデミーが前身で、いくつか場所を変えたのち、現在のパリ9区に1875年に建てられました。「パレ・ガルニエ」とも呼ばれるオペラ座はナポレオン3世によるデザイン・コンペで選ばれたシャルル・ガルニエの建築によるもの。ナポレオン3世の時代の第二帝政を代表する壮麗な建築物で、ネオ・バロック様式の傑作とされています。しかしバスチーユに新しいオペラ座オペラ・バスチーユができて以来、オペラは専ら新オペラ座で上演され、オペラ・ガルニエでは主にバレエが上演されています。カルポーの彫刻を始めとして多くの華麗な彫刻で飾られ、オペラ座の内部も豪華絢爛。別世界に続くような壮麗な大階段が特徴で、その空間設計にはノートルダム大聖堂を参考にしたと言われています。収容人数は1979名。オペラやバレエを観劇しなくても、内部を見学することができます。日本よりお得で観やすいバレエ
オペラ座では主にバレエ公演が行われていますが、日本よりも格段に料金が安く、バレエファンにはおすすめ。また公演の時間帯も19時半や20時などの夜遅くの開演が多いので、昼にはパリ市内を観光して、夕食後にバレエをゆっくり鑑賞することができます。遅い時間帯からバレエを見ることができるため、仕事帰りの男性客も多いです。
パリ改造の主役となったオペラ座
オペラ座の建築が始まった1862年は、まさにパリの街自体が大きく変貌した時期でした(日本で言えば幕末に当たります)。狭く湿気の多い街路を嫌ったナポレオン3世は、セーヌ県知事オスマンに命じてパリの街路を大幅に整理し大通りを切り開いていきます。オペラ座へと向かうオペラ通りも、この時期にできたもの(当時は皇帝通りと呼ばれていました)。オペラ座の前にはオペラ広場ができ、真っすぐな皇帝通り(今のオペラ大通り)が敷かれました。モニュメントへ到達するための通りの整備はオスマンによるパリ改造の重要なプランの一つでした。それ以前、旧オペラ座が立っていたル・ペルティエ通りはとても狭く、ごみごみとした建物がひしめきあっていました。150年前のパリは今のパリとは違い、中世そのものの街並でした。襲撃にあった教訓から作られたオペラ座
ル・ペルティエ通りにあったオペラ座にナポレオン三世が観劇に出かけたとき、テロリストに襲撃されたことがありました。そのときの反省が治安のよい場所にオペラ座を移転するきっかけになりました。
オペラ座の怪人
ナポレオン3世の時代に建設が始まったオペラ座ですが、ナポレオン3世の在位中には完成しませんでした。工事が遅れた原因は、「地下」にありました。基礎工事で地下を掘っていく段階でローマ時代採石場跡が発見され、そこに地下水が流れ込んで巨大な湖ができていたためです。このオペラ座地下に眠っていた湖に着想を得て作られたのが、1910年に発表された『オペラ座の怪人』です。元ジャーナリストの人気作家ガストン・ルルー(1868-1927)は豪華絢爛なオペラ座とその地下にある不気味な湖という対比を見事に描き、オペラ座の地下に住む燕尾服姿の怪人を生み出しました。19世紀に恐怖の対象だった暗い森や城から離れて、パリの都会にゴシック的な恐怖を持ちこんだことが受けたのかもしれません。しかもオペラ座は当時もっとも有名だった建物で、彼の作品は注目を浴びました。その斬新さは今でも多くの人の心を惹きつけ、世界中の劇場で上映され続けています。オペラ座の完成
オペラ座は工事開始から13年後の1875年に完成します。外観は「第二帝政様式」と呼ばれた当時では異様な折衷様式。1月には新オペラ座のオープニングセレモニーがロンドン市長を主賓に迎えて行われました。その時の様子をアカデミーの画家ドゥターユが絵に残しています。オペラ座の完成はパリが変貌した瞬間でもあり、今日私たちが知っている「花の都」が生まれた瞬間でもありました。渋沢栄一が見たオペラ座
日本の近代化に貢献した渋沢栄一(1840-1931)は欧州の最新技術を学ぶために渡仏しました。彼はパリ万博を視察する欧州使節団の一員でした。彼がパリに滞在した1867年当時、オペラ座は残念ながらまだ未完成でしたが、ファサードだけは完成していたそうです。渋沢栄一は改造中の貴重なパリをこの目で見た日本人の一人でした。

ルイ・ベルー(Louis Béroud)作『オペラ座の階段』(L'escalier de l'Opéra) / 1877 / カルナヴァレ美術館所蔵
別世界に誘う大階段
オペラ座の最大の魅力の一つが中央ホールにある大階段です。天井の低い入り口から入った観客が大階段に足を踏み出した瞬間、壮大な空間が天に向かって続いているような感覚に囚われます。セラヴェッツァ産の白い大理石で作られた階段、中央踊り場の美しい丸天井、それを支える壮麗な円柱。まさにオペラという別世界に誘うような演出が大階段によってなされています。ゴシック様式の大聖堂を訪れたような異次元の体験を可能にした大階段は、オペラの世界へと飛翔する夢見装置とも言えます。完成当時のオペラ座の様子を風俗画で評価の高い画家ルイ・ベルー(Louis Béroud)が残していますが、彼がカンバスの中心に描いたのは壮麗な階段でした。オペラ座の美しさの本質は階段にあることを当時の芸術家たちはすでに見抜いていたのでしょう。これから観るオペラへの期待を高めてくれる大階段。オペラを観るという非日常の体験は観劇の前から始まっているのです。シャガールの名画が天井に
オペラ座の内装で大階段と並んで特筆すべきなのは丸天井に描かれた絵画。ロシアの画家マルク・シャガールによる美しい天井画です。『夢の花束』というタイトルの作品で、当時の文化大臣アンドレ・マルローの依頼によって1964年に制作されました。彼は大臣とオペラ座の舞台監督を兼ねていました。シャガールの天井画は今ではオペラ座観光として有名ですが、もともとそこにはフランスの歴史画家ジュール=ウジェーヌ・ルヌヴーの作品『昼と夜のミューズと時間』が描かれていました。その絵は天井画がシャガールに変更されるまでの約92年間、オペラ座の天井を飾っていました。日本人街としてのオペラ座
現在オペラ座周辺は日本人街としても知られています。パリ13区(プラス・ディタリー)や4区(北マレ)にある中国人街とは違い、街としての明確なエリアではありませんが、日本食材店や日本料理レストランが多くあるため日本人をよく見かけます。ラーメンやかつ丼、すし屋など、日本食が懐かしくなったときに便利です(ただし、経営者は日本人でないことが多いです)。お土産を買う日本人が集まるのもオペラ通り周辺です。待ち合わせ場所としても分かりやすいオペラ座正面はいつも多くの人で賑わっています。日本の書店も多く、日本語の書籍が必要な時に便利。ルーヴル美術館にも徒歩圏内で、日本人に人気のデパートプランタンやギャラリー・ラファイエットもすぐ近くです。オペラ座のミツバチ
パリにはほとんど虫がおらず、街はおろかブーローニュやヴァンセンヌの森などを歩いていても出会うことはほとんどありません。これはパリの緯度が高いせいだと言われていますが、夏の風物詩セミの声が聞こえないのはなんとなく寂しい気もします。その中で例外的なのがミツバチ。意外にもパリの街の至る所に飛んでいます。これはサトウキビの栽培以前に蜂蜜がフランス人にとって砂糖の代わりとしての大事な栄養源だったからです。パリには今でもいくつかの養蜂場があり、その中でも面白いのがオペラ座の養蜂場。オペラ座の屋根裏部屋に作られており、チュイルリー公園のミツバチたちが集まってくると言われています。ナポレオンの紋章にも使われたミツバチ。今は美容と健康のために蜂蜜を食べるフランス人が多いようです。パリのお土産に蜂蜜を渡すのもいいかもしれません。- パリ観光基本情報
- オペラ座 / l'Opéra(Palais Garnier)
- パリの観光地
- オープン(完成):1875年
- 住所:Place de l'Opéra, 75009 Paris
- 最寄メトロ:Opera(オペラ)
- エリア:オペラ座周辺
- カテゴリ:パリの観光スポット
- 関連:その他のおすすめパリ観光
オペラ座へのアクセス(地図)
オペラ座へのアクセス(地図)
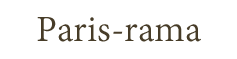 パリ観光サイト「パリラマ」
パリ観光サイト「パリラマ」















