ノートルダム大聖堂

ノートルダム大聖堂とは
パリの中心地シテ島にある聖母マリアに捧げられた教会堂。ノートルダムとは「われらの貴婦人」という意味。1345年に完成した。
パリ観光の中心地へ
パリの発祥地シテ島に建つ大聖堂で、1163年に建造が始まり200年の歳月をかけて1345年(1350年)に完成しました。すでに700年近い歴史を持っています。ゴシック様式の壮麗な外観が特徴の建築物で、パリを代表する観光地です。19世紀に建築家ユージェーヌ・ヴィオレ・ル・ドュックが修復しました。ノートル・ダムとは「われらの貴婦人」という意味で、聖母マリアに捧げられた聖堂です。ノートルダム寺院はフランス各地に存在しますが、パリの大聖堂がその総本山と言えます。国民の8割以上がカトリックというフランスで、毎日多くの市民が祈りを捧げにここを訪れます。ノートルダム大聖堂の最寄り駅は?
メトロで大聖堂へ向かう場合、最寄り駅は地下鉄4号線のシテ駅。シテ島唯一のメトロです。駅のすぐ近くには1808年頃にできた有名な花市場があります。
ヴィクトル・ユーゴーの小説で有名に
またノートルダム大聖堂は、ヴィクトル・ユーゴーの小説『ノートル・ダム・ド・パリ(Notre-Dame de Paris)』の舞台として有名です。『ノートル・ダム・ド・パリ』は1831年にヴィクトル・ユーゴーが発表した小説。この小説を読んだ当時の人々は、ノートルダム大聖堂の歴史的な意味と芸術的な価値を再発見し、当時荒廃していた大聖堂を復元したいと願うようになりました。小説のおかげで、修復工事が始まり、中世の面影を残す現在の美しい姿になりました。フランス文学は国の遺産さえも蘇らせてしまう力があるのかもしれません。映画になったノートルダム
小説『ノートル・ダム・ド・パリ』はハリウッドで映画化されました。ジャン・ドラノワ監督による1956年の映画で、日本語タイトルは『ノートルダムのせむし男
』。アンソニー・クインが主人公のカジモドを演じ、ジーナ・ロロブリジーダがエスメラルダ役を演じました。
ノートルダム大聖堂の外観
ノートルダム大聖堂は中世に流行したゴシック様式で建てられています。写真などでよく見るイメージは2つの四角い塔がそびえる正面です。高くそびえたつ双塔に細かな彫刻が彫られ、訪れた人々に壮大な印象を与えます。また背後から眺めるノートルダムもまた趣があります。その姿は巨大な甲殻類のようにも見えます。中に入ると、暗い入り口から一気に視界が開け、まるで天界へと導かれるような異世界体験を味わうことができます。内部のステンドグラス(バラ窓)や建物の壁面についているガーゴイル(怪物の石像)も有名です。ゴシック様式を代表する建物で、パリ随一の観光名所です。ゴシックの意味は?
ゴシックとは中世ヨーロッパで12世紀から16世紀にかけて発展した建築様式。「ゴート的」という意味で、もともとはゲルマン民族の建築様式を指す言葉でしたが、イベリア半島から伝わったイスラムによる石組建築とノルマンディーから伝わったヴァイキングによる木組建築が融合してできた北フランスの建築を指すようです。尖塔、ステンドグラス、大きな窓、飛び梁(バットレス)などが特徴。有名なゴシック建築物には、ノートルダム大聖堂やケルン大聖堂があります。
大聖堂内の森
光と静寂に満ちた聖堂内に入ると、何か大きな存在に包まれているような不思議な感覚になります。それは例えるなら大自然の森に入った時と同じような感覚かもしれません。実際に大聖堂の尖塔の下には「La forêt ラ・フォレ(森)」と呼ばれる中世時代に作られたオーク材の骨組みがあります。全長約91メートル、高さ約9.1メートルにもおよぶ複雑な構造をした骨組みで、聖堂内にいながら大自然に包まれたかのような壮大な空間を演出しています。すべてが石で作られているように思われるノートルダム大聖堂ですが、実は大都市パリの中心部に出現した仮想現実としての森の役割を果たし、訪問者はそれを無意識のうちに感じ取っています。それはかつてこの地に暮らしていたケルト文化につながるものと考えられています。大聖堂の建設当時、森への信仰の篤かったケルト民族を改宗させるためにキリスト教宣教師たちは聖堂内に森のような空間を作ることを考えました。周辺の森を伐採しそれらの木を骨組みとして用いることで聖堂内に信仰としての森を再現したのです。また森という存在への潜在的な畏怖の感情がガーゴイルという怪物彫刻を生み出したとも言われています。塔から眺望が楽しめる
また作家のヴィクトル・ユーゴーは若い頃ノートル・ダムの塔に登るのが好きだったようで、塔の上からはエッフェル塔などのパリ遠景を眺めることができます。眺望の美しい大聖堂南塔の上へは延々と続く螺旋階段で上ります。高さは69メートル、387段もあります。ちなみに凱旋門の高さは約50メートル。ノートルダム寺院より19メートル低いです。2000年前には多神教の神殿があった
パリがパリと呼ばれる前、この辺りは一面の沼地で、シテ島にはガリア人(パリシイ人)の小さな神殿と葦で葺いた円形のあばら家があるだけでした。その後、ローマ人がこの地を支配し、ルテティアの建設が始まりました。パリの祖となった古代都市です。ローマによる支配後も、シテ島ではガリア人の信仰は残り、ローマの神々と共存することになりました。ローマの最高神ユピテルを祀った神殿が建てられたと言われています。まだキリスト教がこの地へ伝わる前の時代です。ノートルダム大聖堂のあった場所は、当初多神教の聖地だったのです。大聖堂の地下には古代パリの城壁が残る
パリは3世頃から「パリ」と呼ばれるようになりました。当時蛮族の侵入が激しくなり、ローマ都市がセーヌの中に浮かぶシテ島に限定され、島には堅固な城壁が作られました。ローマ人が減り、元々この近く(シテ島とナンテール)に住んでいたガリアの民族であるパリシイ人が住む町になったため、パリと呼ばれるようになりました。その当時の城壁がノートルダム大聖堂広場の地下にあるクリプトに保存されています。保存状態はとてもよく、4世紀のパリの住居跡と歩道の舗石が残されています。ちなみに大聖堂南側の土台は、このローマ時代の城壁の上にすえられています。ノートルダム大聖堂の前にあった大聖堂
ノートルダム大聖堂のあった場所にはローマ時代にユピテルを祀った神殿がありましたが、500年ごろには荒廃し廃墟となっていました。この頃はローマの支配からフランク族の支配となり、フランク王国の首都としての中世のパリが始まっていました。フランク族の王クロヴィスの息子キルデベルトは、廃墟となった神殿のある場所に修道院を建設することを決めました。ローマのサン・ピエトロ大聖堂に匹敵する修道院を建て、新たな精神世界をパリに作るという壮大な計画でした。こうしてフランク王国最大の教会堂であるサン・テティエンヌ大聖堂が完成しました。全長70メートル・幅36メートルでフランク王国最大の教会堂でした。これが現在のノートルダム大聖堂の前身となりました。現在のノートルダム大聖堂の前にある広場には、当時のサン・テティエンヌ大聖堂の正面入り口の様子が敷石で描かれています。木こりの息子だった司教が発案者。180年の歳月がかけられたノートルダム大聖堂の建設
サン・テティエンヌ大聖堂はどのようにして現在のノートルダムに変化していったのでしょう。時代はさらに数百年後、敬虔なフランス国王であったルイ7世が治めたカペー朝の時代。1160年に当時のパリ司教だったモーリス・ド・シュリーは、より壮大な聖堂の建築を計画しました(彼は貧しい木こりの息子から司教に出世しました)。当時のフランスは気候の温暖化と農作物の収穫で比較的安定していましたが、王の離婚によって国の周囲をプランダジネット家(中世のイングランド王朝)に囲まれ、政治的な危機を迎えていました。そのため、ノートルダム大聖堂の建立は国民の意識を国力へと向ける重要な事業として考えられていました。キリスト教への信仰が篤かったルイ7世は宗教の力でイングランドに対抗しようとしたのです。新しい大聖堂の建設工事はそれから60年以上も続きました。1225年に完成しましたが、正面を構成する2つの塔の建設は1250年まで続けられ、最終的に完成したのは14世紀半ばの1345年でした。女神はヘレニズム時代に地中海地方で非常に強い存在でしたし、ローマ・カトリックの伝統において聖母として再生しました。十二、十三世紀のフランスの大聖堂ほど美しく壮大に女神を崇めた伝統は他に見当たりません。その教会のすべてが「われらの聖母(ノートルダム)」と呼ばれていたくらいです。
ジョーゼフ・キャンベル『神話の力』
フランス革命で一部破壊され、その後修復
フランス革命はノートルダム大聖堂にとって危機的な状況でした。反革命派の大本山として破壊されかけました。なんとか難を逃れましたが、聖堂内は剥落し、当時の姿は失われてしまいました。革命後の1804年12月、大聖堂ではナポレオン1世の戴冠式(聖別式)が行われました(その時の様子を描いたジャック=ルイ・ダヴィッドによる巨大な絵画『パリのノートルダム大聖堂でのナポレオン一世の戴冠式と皇妃ジョゼフィーヌの戴冠』がルーヴル美術館に展示されています)。1831年には作家ヴィクトル・ユーゴーが小説「Notre-Dame de Paris(ノートル・ダム・ド・パリ)」を発表します。この小説は当時の人々の心を動かし、ノートルダム大聖堂の歴史的な意味と芸術的な価値を再確認させました。そして当時荒廃していた大聖堂を復元したいという希望が多くなり、ついに建築家ユージェーヌ・ヴィオレ・ル・ドュックによって修復工事が始まりました。工事は20年近くかかりましたが、それまで失われていた尖塔や内陣、後陣が中世当時の美しい姿を取り戻すことができました。
2019年4月、火災によって尖塔が崩壊
しかし21世紀になって、多くのフランス人にとって忘れられない事故が起こります。2019年4月5日午後6時頃にノートルダム大聖堂で火災が発生。一時間後には尖塔が炎に包まれ、崩れ落ちました。大聖堂からは巨大な雲のような煙が立ち上り、多くのパリ市民が大聖堂を囲む通りに集まり、その様子を見守りました。火は12世紀に架けられた木の梁で急速に広がり屋根まで延焼。現場に駆け付けた消防隊約400人の消火活動により可能な限り多くの文化財の運び出しが行われました。その中にはイエス・キリストが十字架に架けられる際に被っていたとされる聖遺物「いばらの冠」や列聖された13世紀の国王ルイ9世が着用していたチュニックなどが含まれているそうです。マクロン大統領は火災現場に駆け付け、「全てのカトリック教徒と全てのフランス国民と共に悲しんでいる。フランスの全国民と同じように自分たちの一部が燃えているこの光景は悲しい」と話しました。火災は翌日16日の午前に鎮火しました。幸いにも後陣の壁を支えるバットレス、北側に配置された薔薇窓、2つの鐘楼は破壊を免れました。パリの中心である大聖堂はパリの歴史そのもの。フランス人の心の拠り所であり、パリのシンボルが失われたことでフランスは大きな悲しみに包まれました。
大聖堂の再建のための工事が開始
火災後、ノートルダム大聖堂は修復のための今までにない大規模な工事が行われました。今回修復を手がけたのは、パリ大司教区が監督するプロジェクト「アトリエ・ド・ノートルダム(Atelier de Notre-Dame)」。このプロジェクトには大聖堂の内部修復に携わったアーティストや専門家たち、様々な企業などが所属していて、「沈黙」をテーマに丁寧な修復作業が行われました。2021年9月には屋根の再建が完了し、2023年1月には尖塔の修復が終了。修復のためにフランス国内外から参加した専門家の数は約1,000人、総工費は約10億ユーロになりました。850年の伝統が続く石造りやステンドグラスの荘厳な雰囲気を守りながら、一流の職人たちの手によってかつての大聖堂の復元が行われたのです。大聖堂の床下からお宝を発見
大聖堂の再建期間中には幸運な出来事もありました。政府による考古学者チーム(フランス国立予防考古学研究所)が聖堂の床下を調べた結果、かつて大聖堂の中心に置かれていた芸術作品が発掘されました。その中には建築物を象った装飾用の彫刻やキリスト像の一部、13世紀の内陣仕切り、彫刻の手の部分などがありました。色彩が施された彫刻もあり、当時のノートルダム大聖堂は色鮮やかな彫刻で飾られていたと推定されています。今回の発掘調査で見つかった作品のうち約30点がカルチェラタンにあるクリュニー中世美術館で開催された「石の声を聴く。ノートルダムの中世の彫刻」展で展示されました(2025年3月まで)。修復を終え2024年末に再び一般公開
2024年末に内装を含めた全ての修復が完了し、ノートルダム大聖堂は再び一般公開されました。今回の大規模な再建で火災によって損傷する以前の姿が蘇ったことはフランスだけでなく世界的に大きなニュースとなりました。火災で崩壊した尖塔は、ヴィオレ・ル・デユックのデザインを元に修復され、高さ12メートルの十字架も再建。内部を飾る約40枚のステンドグラス、壁、23枚の絵画、有名なガーゴイルを含む54体の石像、アーチが綺麗に清掃され、8000本のパイプを持つオルガンや白黒のチェックの床も修復されました。熟練の職人たちの手によって、大聖堂は以前と同じ姿を再び見ることができるようになりました。またその一方で、新たなデザインに変更された場所もあります。2026年までには現代的なステンドグラスが設置予定で、また聖堂内のお土産売り場が現代的なデザインにリニューアルされました。フランス屈指の観光スポットでもあるノートルダム大聖堂は、再開後は年間で1200万から1500万人の訪問者を迎えると予想されています。ひどい孤独感に襲われながら、それでいて自分はこの世界の一部であると感じるのは不思議なものだ。ノートルダム大聖堂の前の広場を埋めつくしている群衆の端に立っていると、その感覚がよみがえった。人が多すぎて大聖堂のなかに入っていけそうにもなかったが、アンプのおかげで音楽は広場の隅々にまではっきりと聞こえた。曲名を知らないフランス語のクリスマス・キャロル。「きよしこの夜」。
パトリシア・ハイスミス『太陽がいっぱい』
- パリ観光基本情報
- ノートルダム大聖堂 / Cathédrale Notre-Dame de Paris
- パリの観光地
- オープン(完成):1345年
- 住所:6 Parvis Notre-Dame - Pl. Jean-Paul II, 75004 Paris
- 最寄メトロ:シテ(Cite)
- エリア:シテ島
- カテゴリ:パリの観光スポット
- 関連:その他のおすすめパリ観光
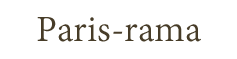 パリ観光サイト「パリラマ」
パリ観光サイト「パリラマ」















