ビラ・ケム橋
最終更新日:

ビラ・ケム橋
橋の上をメトロが走る!二重構造のダイナミックな橋
ビラケム橋(ビル・アケム橋)は高級住宅街パッシーの16区と日本文化会館のある15区を結ぶ美しい橋。その見栄えの良さから映画の撮影にもよく使われています。この橋の特徴は二階建であること。橋の上に車道と歩道があるのは他の橋と変わりませんが、そのさらに上をメトロが走っています。セーヌを渡り高級住宅街の中に消えていく光景はパリで最も美しいメトロ風景かもしれません。川から橋を見ていると不意に現れる列車は迫力満点。それはなんだか16区のアパルトマンの中から急に飛び出してきた未来の乗り物のように見えて面白い風景です。アレクサンドル3世橋のような豪華絢爛さはありませんが、シックな美しさを持っているビラケム橋。この橋独特の二重構造が、まるでローマの水道橋を思わせる重厚さをかもし出しています。デンマークから寄贈されたジャンヌ・ダルクの像
ビラケム橋の真ん中まで歩くと勇壮な騎士のような像が見えてきます。これはフランスの英雄と言われるジャンヌ・ダルクの像。デンマークがフランスに寄贈した彫刻ですが、当時はその好戦的な姿が時代の空気に合わず、像を受け取るフランス側に迷いがあったそうです。しかし像に「フランスの復活」(La France Renaissante)という意味をつけることで、フランス国家の偉大さを象徴することができ、この橋に置かれることになりました。

ビラ・ケム橋
ビラケム橋の歴史
この橋の完成は1878年。万国博覧会のために歩行者専用の橋として造られました。パリの メトロの完成は1900年なので、完成当時はまだ橋の上には列車が走っていませんでした。名前もビラケム橋ではなく、パッシー歩道橋と言われていたのです。 パリのメトロが開通して数年後の1903〜1905年に橋の改築工事が行われ、メトロの鉄橋と2車線の車道が加えられました。まだメトロが最新の乗り物だったときです。中央の歩行者通路に並ぶ無限連鎖のような鉄柱は、1937年に当時アール・ヌーヴォー様式だった柱を機能的な柱へと作り変えられもの。その後橋の名前がビラケム橋に変更され、現在に至っています。名前の由来はリビア砂漠のオアシス
ビラケムという名前は北アフリカのリビアにあるオアシスの地名から取られました。第二次世界大戦中の1942年にビラケム(ビル・アケイム)でフランス軍とドイツ・イタリア軍が闘い、最終的に包囲網を破ったことを記念して命名されました。

ビラ・ケム橋
ビラケム橋が舞台となった映画
ビラ・ケム橋はパリらしい都市美と叙情を合わせ持つロケーションとして多くの映画の舞台にもなっています。その中でも特に評価の高い作品をご紹介します。『ラストタンゴ・イン・パリ』ベルナルド・ベルトルッチ監督(1972 / イタリア)
妻を亡くし人生に絶望した中年男と結婚間近である若い女の匿名的な性的関係を描いたイタリア映画。パリの高級住宅街であるパッシーが主な舞台となっていて、冒頭のシーンではビラケム橋で二人がすれ違う姿が描かれています。二人は偶然にも同じ貸しアパートを内覧しに行く途中で、主人公ポールがそのアパートで出会ったばかりの若い女性ジャンヌを襲う場面が描かれています。美しいビラケム橋とその上を走るメトロの風景が何度も映画の中に登場し、物語の節目の役割を果たしています。主演はマーロン・ブランドとマリア・シュナイダーで、強烈な感情と破壊的衝動が交錯する心理描写が特徴。公開当時、激しい性暴力的な描写が観客に衝撃を与え、多くの国で検閲や上映禁止の対象になりました。批評家からはブランドの演技とベルトルッチの類まれなる映画美学への賛辞と同時に、性的暴力的な演出と主演女優への配慮のなさについて厳しい批判も集まりました。2025年にはこの映画の裏側にあった「女優マリア・シュナイダーの葛藤と怒り」に焦点を当てた伝記映画『タンゴの後で』が公開されました。脚本はマリアのいとこであるル・モンド紙のジャーナリスト ヴァネッサ・シュナイダーによる著作『あなたの名はマリア・シュナイダー』が原作。監督はベルトルッチ監督の『ドリーマーズ』でインターンをしたジェシカ・パルー。主演はアナマリア・ヴァルトロメイ、マーロン・ブランド役をマット・ディロンが演じ、70年代最大のスキャンダルといわれた映画の撮影時の権力構造と映画界における女性の搾取を厳しく描き出しています。
『アメリカの友人』ヴィム・ヴェンダース監督(1977 / 西ドイツ・フランス)
パトリシア・ハイスミスの小説が原作のクライム・サスペンス。アラン・ドロンが演じた『太陽がいっぱい』の元になった小説『リプリー("The Talented Mr. Ripley")』はリプリーシリーズ(連作)として知られ、その3作品目である『贋作』("Ripley’s Game")がこの映画の原作です。主な舞台はハンブルクですが、平凡な暮らしをしていた額縁職人ヨナタン(ジョナサン)がマフィアの殺人依頼を受けてパリに行くシーンでビラケム橋が登場します。ヨナタンが泊まったホテルがパリ15区にあるホテルで、依頼者が宿泊するホテルがセーヌを隔てた対岸のパリ16区にありました。2つのホテルを結ぶのがビラケム橋で、ヨナタンが殺人を決意して橋を渡る場面では彼の意識の流れを巧みに表現する手段として橋が効果的に使われています。ビラケム橋が登場するその他の映画
他にもルイ・マル監督のデビュー作『死刑台のエレベーター』(1958)やわんぱく少女の視点から見たコミカルなパリを描いた『地下鉄のザジ』(1960)、連続殺人犯を追う警部をジャン=ポール・ベルモンドが演じたアンリ・ヴェルヌイユ監督の『恐怖に襲われた街』(1975)、主人公の姿が出てこないパリ風景のみを描いたマルグリット・デュラス監督の『船舶ナイト号』、CGを駆使して不可思議なパリを映像化したクリストファー・ノーラン監督の『インセプション』(2010)など多くの映画の舞台として登場しました。
ビラ・ケム橋
メトロに乗ってビラケム橋を渡ろう
またメトロに乗ってこの橋を渡るのも面白い体験です。15区のビラ・ケム駅から乗れば、セーヌを渡る間に高級住宅街パッシーの壁のような建築物が迫り来るほどの迫力で見られます。ビラ・ケム橋を渡るときに突如セーヌ河の向こうに現れるエッフェル塔には、誰しもが感動することでしょう。またビラケム橋からは7月14日の革命記念日の花火もよく見えるそうです。
白鳥の小径へはビラ・ケム橋の途中から降りられる
ビラケム橋の近くのパリ観光
ビラケム橋の16区側はパッシーという高級住宅地。観光ではないパリの雰囲気を知りたい方は散策してみるといいかもしれません。15区側には日本映画の特集上映などを行う日本文化会館があります。またこの橋の中央からセーヌの中洲白鳥の小径に降りることもでき、散策やジョギングにも最適です。隣のグルネル橋までも歩いていけます。エッフェル塔までも徒歩圏内。- パリ観光基本情報
- ビラ・ケム橋(Pont de Bir-Hakeim)
- パリの観光地
- オープン(完成):1878年
- 最寄メトロ:Bir-Hakeim(ビラケム)、Passy(パッシー)
- エリア:パッシー、グルネル
- カテゴリ:パリの観光スポット
- 関連:その他のおすすめパリ観光
ビラ・ケム橋へのアクセス(地図)
ビラ・ケム橋へのアクセス(地図)
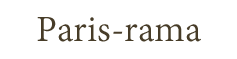 パリ観光サイト「パリラマ」
パリ観光サイト「パリラマ」



















