おすすめパリ散歩:バスティーユ広場から南マレを抜けてパリ市庁舎へ
このモデルコースの概要
活気あふれるバスティーユからマレ地区の元邸宅(美術館)を巡り、壮麗なパリ市庁舎へ向かうパリ散策コース。パリ初の公共広場だったヴォージュ広場やユダヤ文化が体験できるロジエ通りも訪れます。

出発は革命の発端となったバスティーユ広場から
まずはパリで最も古いメトロ1号線に乗り、バスティーユ駅で下車。メトロの階段を上がると広い空が広がる開放的なバスティーユ広場に出ます。バスティーユ地区は今若者の間で人気のパリエリア。パリ11区、12区、4区の境にあり、パリ中心部からは離れていますが、最新のカフェやバーが店を開き、今ではパリジャンに人気のナイトスポットになっています。もともとはフランス革命の発端になったバスティーユ牢獄があった場所で、広場の名前もその牢獄に由来しています。中央には黄金色に輝く自由の天使の像が乗った革命記念柱が建っています。これは1830年の7月革命の犠牲者を追悼して1833年に作られたもの。現在バスティーユ広場には新オペラ座(オペラ・バスティーユ)もあり、新しい芸術の発信地としても知られています。また下町フォブール・サン・タントワーヌにも近いこともあって、気さくな雰囲気が漂い、気どらないパリの姿を見ることができるのも魅力です。
ヴィクトル・ユゴーの家があるヴォージュ広場へ
革命の始まりとなったバスティーユ広場からサン=タントワーヌ通りを西に歩きます。この通りはフランス革命をテーマにしたチャールズ・ディケンズの小説『二都物語』の舞台にもなった職人街。貧しい暮らしをしていたパリの職人たちの怒りがこの通りで一気に燃え上がり、物語はクライマックスへと進んでいきます。家具職人の工房が今も多く残っていて、椅子のアトリエがある小径を歩くのも面白い。最初に訪れるのはマレ地区の代表的な観光地とも言えるヴォージュ広場。パリ4区、マレ地区にある正方形の美しい広場で、四方をルネサンス様式の赤レンガの館に囲まれています。パリで初めて作られた公共の広場としても知られていて、かつて「広場」と言えばこのヴォージュ広場を指していました。広場中央には1639年に建設され1829年に復元されたルイ13世の騎馬像が立っています。庭には左右対称となるように設計された4つの泉があり、その周りでは広場を訪れたパリ市民が気持ちよさそうに思い思いの時間を過ごしています。ヴィクトル・ユゴーの家
広場を囲む館の一角にあるロアン・ゲメネ館(Hotel de Rohan-Guemenee)は作家ヴィクトル・ユゴー(1802-1885)が住んだ家として知られています。彼がこの館に引っ越してきたのは世界的に有名な代表作『ノートルダム・ド・パリ(Notre Dame de Paris)』が出版された一年後でした。現在ユゴーの家は記念館(Maison de Victor Hugo)になっていて、小説家・詩人として活躍した作家の人生をたどることができます。

老舗デパート「ラ・サマリテーヌ」の創業者の美しいコレクションを見る
ヴォージュ広場を出たら、フラン・ブルジョワ通りを歩いてみましょう。この通りにはオシャレなブティックが多く買い物にも最適。女性向けのブティックや香水専門店、ジュエリー、ブーツ、腕時計のお店などがたくさん並んでいます。日本の有名な衣料品店ユニクロもこの通りに出店しています。エルズヴィール通りを右に曲がると右手に美しい庭と邸宅が見えてきます。この建物はコニャック=ジェイ美術館。18世紀の美術品を集めた美術館で、元はドノン館という14世紀に建てられた貴族の館でした。この美術館の所蔵品はパリの老舗デパート「ラ・サマリテーヌ」の創業者エルネスト・コニャックとマリー=ルイーズ・ジェイ夫人のコレクションが元になっています。デパートで成功を収めた夫妻は18世紀の美術品を中心に集めており、死後彼らのコレクションがパリ市に寄贈されました。
ユダヤ人街で名物料理ファラフェルを食べ歩き
美術館を出た後は元来た道を戻り、石畳のパヴェ通りを抜けてロジエ通り(Rue des Rosiers)に入ります。ロジエ通りはマレ地区にある小さな通り。交差するエクーフ通り(Rue des Ecouffes)と並んで、パリ4区に形成されたユダヤ人地区を代表する通りです。通りの名前であるロジエは「バラの木」という意味で、ここがまだパリ郊外だった13世紀頃につけられたと言われています。この辺りはパリのユダヤ街の中心的な界隈で、ユダヤ移民たちの日常を垣間見ることができます。イスラエルの屋台料理ファラフェルのお店が幾つかあり、パリの名物ファーストフードとしてパリジャンにも観光客にも人気です。散策では是非ファラフェルを買って食べ歩きしてみましょう。ファラフェルは公園で食べる
ファラフェルは食べ歩きにぴったりのファーストフードですが、けっこうボリュームがあります。近くにあるシャルル・ヴィクトール・ラングロワ公園(Square Charles-Victor Langlois)のベンチでドリンクと一緒にゆっくり味わうのがおすすめです。教会(Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux)の隣にある公園で、園内には卓球台や遊具があります。

ジャンヌ・ダルクの手紙が残る国立公文書館へ
公園でファラフェルを食べたら、再びフラン・ブルジョワ通りを西に向かって歩きます。アルシーヴ通りとの角に見えてくるのは2つ目の貴族の邸宅であるスービーズ館。ルイ14世の時代、1705-09年にかけて建築家ピエール・アレクシス・ドラメールによって建てられた豪華なロココ様式の館です。ロココ(Rococo)とは、バロック様式のあとにやってきた優美で繊細な芸術様式のこと。「洞窟の岩組」を意味するロカイユ(Rocaille)が名前の由来で、ルイ15世の宮廷文化から始まった彩色豊かで贅沢なデザインが特徴。18世紀には多くの文化人が集まり、サロンや演奏会が開かれたそうです。フランス革命時に政府に没収され、現在はフランス国立公文書館(Archives nationales)になっています。見どころはジャンヌ・ダルクの手紙やルイ16世とマリー・アントワネットの遺書など。他にも中世の資料やアンティークの家具、18世紀の絵画などが展示されています。
ネオ・ルネサンス様式の壮麗なパリ市庁舎へ
国立公文書館を出たらアルシーヴ通りを南に下り、今回の散策の最終目的地であるパリ市庁舎(オテル・ドゥ・ヴィル)へ。パリ市庁舎は、1357年に建てられたネオ・ルネサンス様式の壮麗な建物。14世紀から今と同じ場所にあり、600年以上の歴史があります。フランス革命の始まった1789年には、ヴェルサイユ宮殿を逃れた国王ルイ16世を迎え、3年後には革命政府の拠点となりました。1871年のパリ・コミューンの際に一度焼失しましたが、1882年に再建され今に至っています。パリ市庁舎の中では無料の写真展などもよく行われており、観光客でも気軽に立ち寄ることができるのが魅力です。愛の街パリを象徴する写真
パリ市庁舎と聞いてフランスの国民的写真家ロベール・ドアノーの有名な写真を思い出す人も多いのではないでしょうか。彼の撮った写真『パリ市庁舎前のキス』のおかげでパリ市庁舎は世界的に有名になり、この写真は愛の街パリを象徴する1枚となりました。ただこの写真は偶然に撮られたものではなく、ドアノーによる芸術的な演出でした。その熱意あふれる撮影秘話はドキュメンタリー映画『パリが愛した写真家 ロベール・ドアノー 永遠の3秒』で見ることができます。
- パリ観光基本情報
- パリのオススメ散策コース
- コース内で紹介した観光スポット:バスティーユ広場、ヴォージュ広場、コニャック=ジェイ美術館、ロジエ通り、国立公文書館、BHV、パリ市庁舎
- 所要時間:3時間
- 利用メトロ:バスティーユ(Bastille)、オテル・ドゥ・ヴィル(Hotel de Ville)
- エリア:マレ地区
- カテゴリ:パリおすすめコース
- 関連:パリの人気観光スポット
散策で通ったパリのエリア・スポット
パリラマはパリを紹介する観光情報サイトです。パリの人気観光地からあまり知られていない穴場まで、パリのあらゆる場所の魅力を提供することを目的としています。情報は変更される場合があります。最新情報はそれぞれの公式サイト等でご確認ください。
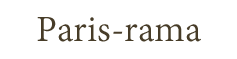 パリ観光サイト「パリラマ」
パリ観光サイト「パリラマ」












